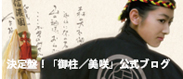2009年05月03日
共食の文化 其の一
「共食の文化」について書いてみたいと思います。
「共食の文化」は素晴らしい日本文化です。
おそらく「食」というものが生活の中心としてデザインされている文化とも言えるかも。
その起源は縄文時代・旧石器時代にまで遡ることが出来るようです。
現在の私たちにわかりやすい事例では「お鍋とか焼き肉」などがそれにあたると思います。
鍋や鉄板は人が輪を囲み、みんなで食べるという文化です。
この「鍋を囲んでみんなで食べる」ことで世代を超えコミュニティーの基礎になるものが
次の世代に受けつがれたり、地域の中の情報共有が円滑になったり・・・
みんなで食べるということはそれだけで・・・いろんな効果があります。
昔の人たちは本当に素晴らしいですね。
昨日の犀川のバーベキューもその例ですね。
子供と大人が河原で遊んだり・・・鉄板や網を囲んでみんなで食べると
自然と世代を超えた交歓が産まれたりして・・・とても素晴らしいものです。
(自然の中ならなおさら良いですよね。)
私は毎月満月の日に縄文の女神LIVEを行っていますが、
その中で縄文ミニトークというコーナーがあり、
大竹幸恵さんという考古学者の方にお手伝いいただき
縄文時代の生活や文化を勉強させていただいています。
その中のお話で「共食の文化」の素晴らしさを認識させられたわけです。
旧石器時代から明治維新まで変わらなかった
「食が中心にある共食の文化」にはこれからの時代を生きる
ヒントが沢山あると思います。
縄文の女神LIVEの縄文トークの中でそれに関わるトークがあります。
縄文時代のお話が中心ですが日本の共食文化の基層がわかります。
その大竹幸恵さんのトークの動画が残っているので
興味のある方はぜひ、ご覧ください。
(縄文時代では土器や石を住居の中心に置きそこでみんなが食べて、
家族や地域のコミュニケーションをはかっていたというお話など)
“灯りを灯す土器、厨房を真中にした縄文住居”
私はこの「共食の文化」を伝えていきたいという想いが
日々、大きくなってきています。
また日をあらためて其の二に続いていきたいと思います。
(明日から二日間、高山に行きますのでブログはその間、お休みかもしれません。)
Posted by 葦木啓夏(Hiroka Ashiki) at 23:43│Comments(3)
│日々の活動
この記事へのコメント
けして寒かったせいではありませんが、口(頭?)が回らず、50~60畳と言いたいのを、5~6畳といっている私です。許してちょ(あはは…苦笑)。
Posted by もへ at 2009年05月05日 21:23
どんなことを次世代に引き継いでいくかは。
その時代にもよると思いますが・・・
良い文化を育み残してあげたいですね。
話は変わりますが、
僕の母はほぼ毎回、縄文の女神LIVEに来てくれているけど
それだけでも僕の励みになったりしています。
このもへっちのお話。
母は泣いて聞いてくれていたのが
とても印象に残っています。
その時代にもよると思いますが・・・
良い文化を育み残してあげたいですね。
話は変わりますが、
僕の母はほぼ毎回、縄文の女神LIVEに来てくれているけど
それだけでも僕の励みになったりしています。
このもへっちのお話。
母は泣いて聞いてくれていたのが
とても印象に残っています。
Posted by 篠原 at 2009年05月06日 17:48
いつもお世話になっています。
バーベキューの件
我々で作っている作物
ナス 長なす・丸なす
キウリ
トマト ミニトマト しし唐、ズッキーニ、ジャガイモ
たまねぎ
上記のもの全てではなくても、使用するバーベキューが希望です。
また、場所が大町・松川なので豚や信州新町のジンギスカンも
いいかもなんて素人で考えておりますが・・・
ご検討お願いいたします。
バーベキューの件
我々で作っている作物
ナス 長なす・丸なす
キウリ
トマト ミニトマト しし唐、ズッキーニ、ジャガイモ
たまねぎ
上記のもの全てではなくても、使用するバーベキューが希望です。
また、場所が大町・松川なので豚や信州新町のジンギスカンも
いいかもなんて素人で考えておりますが・・・
ご検討お願いいたします。
Posted by 長野朝日放送 山口 at 2009年07月16日 16:07