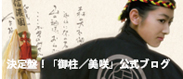2009年05月14日
神長官裏古墳、発見!

さかのぼりますが、11日。篠原さんの旅路を見送った帰り道、
諏訪大社上社・前宮と本宮に通っている道のなかほどにある
「神長官守矢史料館」に寄ってみました。
茅野市宮川出身の世界的建築家・藤森照信さんが設計されことでも有名ですが、
長く諏訪大社上社の旧神長官(神主長・事務長的な職務)を継承してきた
守矢神長官家に伝わる歴史的資料を公開している資料館です。
さっそく突入と思いきや・・・休館日でした。ガーン。
せっかくなので辺りを散策してみました。そしたら・・・

“神長官裏古墳”なるものを発見しました。
神長官裏古墳は、高部古墳群の中で唯一つ墳丘、石室の保存されている古墳である。
この他、神袋塚・塚屋・疱瘡神塚・甑塚がこの北側上方の台地に点在したが消滅した。
墳丘は、高さが北裾から約2米、東西の径9.5米、南北の径9米であるが、
当初はもっと大きな規模の円墳であったと推定される。玄室は長方形で、
奥にしたがって若干狭くなり、長さ3.75米、入口幅1.75米、高さは2.3米である。
石材は安山岩の他数種の石を混用し、側壁は大小の河原石を穹窪状に積み、
天井石は板状節理の磐石を用いている。大正13年に調査が行われ、木炭・木棺破片・
弥生式土器片・碁石・獣骨片・直刀折片・刀子茎残片が検出されたといわれる。
弥生式土器・碁石・獣骨片は後に混入したものであろう。奥壁の左側磐石が抜き取られて
欠損開口し、入口は東南に向くが天井石が崩れてふさがれ、表道部は破壊されている。
築造年代は7世紀頃と推定される。 昭和53年3月 茅野市教育委員会

入口がぱっくり開いていて、向こう側の光が望めます。
どんなかたが、この古墳で安らかにお眠りになっていたのでしょうか・・・。
なんだか、民話・甲賀三郎の中にでてくる地底の国へとつづく穴のようにも思えました。
(私が先日、はなしもの まぐさんから聞いた甲賀三郎のお話は、リンク先のストーリー
とだいぶ違いました。地域によって伝えられ方が変わっているんでしょう。)

ちなみに守矢家の七十八代を継承された守矢早苗さんの「守矢神長家のお話し」に
神長官裏古墳は・・・
『千二百年以上前の遺物です。用明天皇の御世の我が祖先武麿君の墳墓です。』
とあったことを検索するうちに知りました。(情報元・衆生所有楽さん)
蘇我氏に敗れた物部弓削守屋の次男・武麿が諏訪の守屋山に逃れたという話が
あるそうですが、その武麿君のことでしょうか。
いずれにしても、遠い遠い古代のお話と、今に続く歴史のむすびを担う
大切な遺跡だなぁ・・・と感じました。
Posted by 葦木啓夏(Hiroka Ashiki) at 11:22│Comments(2)
│史跡・遺跡・考古学
この記事へのコメント
横穴式の古墳は、何度か入った事があります。たしかにあの古墳の中の暗さには、別世界にいってしまうような恐さを感じました。三郎伝説は、子供の頃読みました。とても懐かしいですね。
Posted by 芹沢 at 2009年05月14日 23:49
前宮の巣籠り神事・・・を連想しました。
盆踊りなどもそうですが日本人の死生観は縄文時代から
深いところで脈々と、ひきつがれてきたように思います。
善光寺街道を歩いてもすごくそのことを感じてきました。
死と再生の輪廻の輪が遠い遠い太古からつながってきている・・・
その強さ、その底知れない奥深さ・・・
その閉じられてきた死と生への扉が開かれつつある
感覚とともに恐さというか、いうにいえない
畏敬の念というかが湧いてきます。
これはイメージでは「龍」ですね。
太古の人たちはこういうわけのわからない恐れの感覚を
共有するために風や龍や蛇などを
信仰の対象にしたのだと思いますね。
盆踊りなどもそうですが日本人の死生観は縄文時代から
深いところで脈々と、ひきつがれてきたように思います。
善光寺街道を歩いてもすごくそのことを感じてきました。
死と再生の輪廻の輪が遠い遠い太古からつながってきている・・・
その強さ、その底知れない奥深さ・・・
その閉じられてきた死と生への扉が開かれつつある
感覚とともに恐さというか、いうにいえない
畏敬の念というかが湧いてきます。
これはイメージでは「龍」ですね。
太古の人たちはこういうわけのわからない恐れの感覚を
共有するために風や龍や蛇などを
信仰の対象にしたのだと思いますね。
Posted by 篠原 at 2009年05月15日 07:48