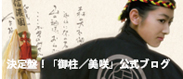2009年10月28日
徳島の神社参拝~龍脈・卑弥呼・鏡・タケミナカタ~
今日はぽかぽか天気の中、主に徳島市内、近郊の神社・史跡・遺跡をめぐりました。

阿波史跡公園
↓
八倉比売神社
↓
多祁御奈刀弥(タケミナトミ)神社
↓
上一宮 大粟神社
↓
一宮神社
↓
金山神社・立岩神社
↓
阿波国一の宮・大麻比古神社
↓
諏訪神社
信濃と阿波の共通点・・・みなさん、知ってますか?
いろいろあるかも知れませんが、日本を縦断する大断層・中央構造線で
結ばれていることが大きいと思います。
私の住む長野県茅野市の杖突峠は、日本海から太平洋に抜けるフォッサマグナと
千葉から九州に抜けていく中央構造線が十字に交わる場所として知られ、
その場所に、シンボリックな存在として諏訪大社があります。
諏訪と阿波の不思議な共通点を探ってみたくて、徳島の地に訪れました。
さて、その不思議に少しは近づけたかな?
さぁ、出発です!

阿波史跡公園
↓
八倉比売神社
↓
多祁御奈刀弥(タケミナトミ)神社
↓
上一宮 大粟神社
↓
一宮神社
↓
金山神社・立岩神社
↓
阿波国一の宮・大麻比古神社
↓
諏訪神社
信濃と阿波の共通点・・・みなさん、知ってますか?
いろいろあるかも知れませんが、日本を縦断する大断層・中央構造線で
結ばれていることが大きいと思います。
私の住む長野県茅野市の杖突峠は、日本海から太平洋に抜けるフォッサマグナと
千葉から九州に抜けていく中央構造線が十字に交わる場所として知られ、
その場所に、シンボリックな存在として諏訪大社があります。
諏訪と阿波の不思議な共通点を探ってみたくて、徳島の地に訪れました。
さて、その不思議に少しは近づけたかな?
さぁ、出発です!

まず訪れたのは、徳島市国府町の阿波史跡公園。
ここは、西日本最大級の縄文後期の集落跡が発見された場所です。
つまりこの公園自体が大きな史跡であり、古墳もあります。明るく、すてきな空気でした☆
徳島 邪馬台国説というのがありますが、まさにその説を唱えている場所でもあります。
邪馬台国・・・と来れば卑弥呼ですね。
卑弥呼・・・といえば鏡なわけなのですが、その共通点はこの遺跡から
日本最古の水銀朱(朱・丹生について)を精製する「たたき石」が見つかっていることが
大きいのかなと感じました。古代祭祀において特別な意味をもつ水銀朱精製技術が
この地で栄え、もしかしたら卑弥呼の祭祀を支えていたのでは?

そして、この遺跡の近くには、八倉比売神社があります。
この神社のご祀神は八倉比売命(ヤクラヒメノミコト)。
=大日霊女命(おおひるめのみこと)と言われており、大日霊女命は、卑弥呼のことでは
ないかという説があります。そんなわけで、邪馬台国阿波説がうまれたのでしょうか。
古代ロマン、広がっていきますね☆

次に訪れたのは、阿波の名方にある多祁御奈刀弥(タケミナトミ)神社。
本居宣長の説によると、諏訪大社の御祭神・建御名方命(タケミナカタノミコト)の名前は
阿波国名方に由来するのではとのこと。(参考:http://www.tohyamago.com/rekisi/chuoukouzousen_suwa/index.html )
全国に一万あるといわれている諏訪神社の総本社
信濃一之宮・諏訪大社のルーツ、真相にふれてみたくて訪れました。
現地に行ってみると、ひとりのご年配の方が境内をお掃除をされていました。
その方はお話を伺ってみると10年間、大総代をされていた方でした。
「この神社、今はこんなにも冴えない神社ですが・・・
昔は豪社と言われ信州の諏訪大社よりも
古くからタケミナカタを祀っているという話が残されています。
昔は随分と栄えていたと伝えられているのです。
私は10年くらい大総代をしていたので古文書などの「証拠」がないか、
随分、方々を訪ね歩き、探し回ったけれど結局、証拠と言えるものは
出て来なかった・・・」というお話でした。
私たちが信濃・諏訪大社よりも先に、ここ多祁御奈刀弥神社に
タケミナカタが祀られていたかもしれないという情報を知って
信州からやってきたことをお伝えすると、とても喜ばれて
「遠方からよくきてくださった。それはそれは・・・」と言ってくださいました。
その言葉を聞いて涙が出そうなくらい感動し、
本当、来て良かったと思いました。
なにか心の中のひっかかりがとれたような・・・不思議な感じでした。

本殿前のしめ縄に付けられた薙鎌。
薙鎌は諏訪大社と共通ですね。風封じ・風鎮めの象徴。風は龍神。
そして、中央構造線(龍脈・タケミナカタ)を封じる薙鎌の力。
(または薙鎌に封じられる力としてのタケミナカタ)。
諏訪との大きな共通点を発見しました。
いよいよ、タケミナカタの封印が解かれるのかもしれません☆


さてさて、八倉比売命のルーツを辿り、徳島市の隣町・神山町にある
上一宮 大粟神社に行きました。
八倉比売命が祀られているのは、こちらの神社が徳島近郊では一番古いようです。
その意味でも素晴らしい古社。こういう神社に訪ねられるのはとても幸せだと思いました。
この神社は大宜都比売命(オオゲツヒメノミコト)と八倉比売命を祀ります。
大宜都比売命は、食物五穀・衣類に関わる大切な神さまです。
伊勢国丹生の郷より神馬に乗り、八柱の供神を率いて阿波国に移られ国土を経営し、
粟を蒔き、当地一帯にひろめられたという。
伝承が残っています。そして、やはり境内には磐座がありました。
阿波はいろんな意味で邪馬台国、大和を支える生産拠点だったのかもしれませんね☆

道の駅・神山でアイスクリームを。
徳島名物「すだちのシャーベット」、さわやかでした!
神山町には、他にも面白そうな史跡がたくさん。またゆっくり巡りたいなと思いました。
そして、次の目的地に向かうことに。

徳島市・一宮町 一宮神社。
上一宮 大粟神社の里宮というか・・・上一宮 大粟神社から勧請された
大宜都比売命と八倉比売命が祀られています。
この神社では、延喜式に書かれているということで
大宜都比売命と八倉比売命は同一神、ということになってました。

次に向かったのは、徳島市・多家良町立岩にある金山神社。
古来、この地に銅の製練・鋳造所があったと伝えられている神社です。
鍛冶の神さま・金山毘古神を主祭神とし、境内には八咫の鏡を製作した
天津麻羅が祀られています。
古代金属器の製作集団の拠点で、祭祀で使われる鏡もここで生産されていたらしく・・・
(たたら場跡があるのです)
日本の最古の冶金技術・発祥の地と推定されています。

金山神社の境内に位置する立岩神社。
まさしく立派な陽石の磐座(イワクラ)です。
午前中に行った神山町に、この磐座と対をなす、もうひとつの立岩神社があるそうです。

そして、阿波国一の宮・大麻比古神社へ。
神武天皇の時代。麻の生産拠点として阿波の地が選ばれたそうです。
その痕跡が・・・大麻比古神社神社です。


今日、最後に徳島のシンボル眉山(びざん)にある諏訪神社に行きました。
一日の最後に相応しい素敵な神社でした☆
こうして一日の軌跡を眺めると、
まだまだ不鮮明なことが多いけど・・・
中央構造線に導かれて、邪馬台国、卑弥呼、タケミナカタ、鏡が
静かに結びつきはじめている気がします。
ここからなにに導かれていくのでしょう。
明日からの展開も、とても楽しみです☆
Posted by 葦木啓夏(Hiroka Ashiki) at 23:45│Comments(1)
│史跡・遺跡・考古学
この記事へのコメント
卑弥呼が使った水銀朱と、
水銀朱の産地・中央構造線とが交わり深く
関係していた徳島・阿波の国。
邪馬台国・大和において食糧・麻・銅製品・水銀精製と塗装など・・・
基幹的な産業拠点であったことは間違いなさそうですね。
古の龍の力の封印が解かれる感覚でした。
水銀朱の産地・中央構造線とが交わり深く
関係していた徳島・阿波の国。
邪馬台国・大和において食糧・麻・銅製品・水銀精製と塗装など・・・
基幹的な産業拠点であったことは間違いなさそうですね。
古の龍の力の封印が解かれる感覚でした。
Posted by 篠原 at 2009年10月28日 23:55